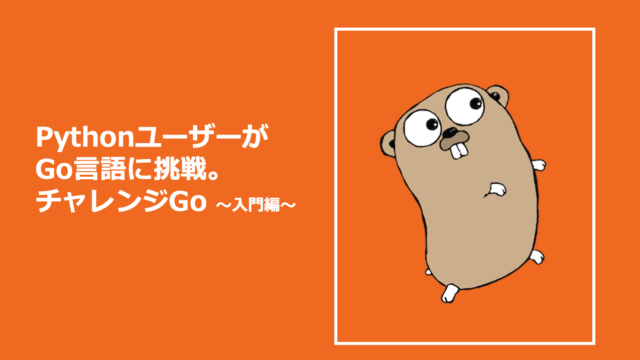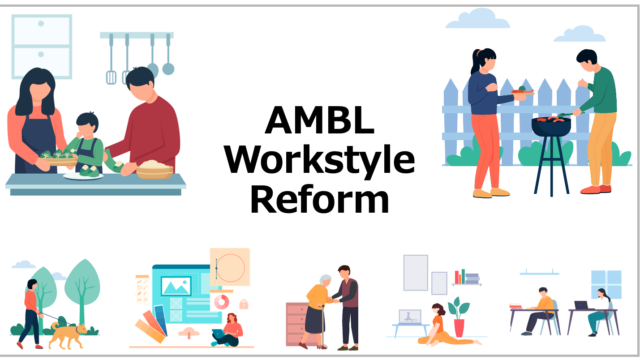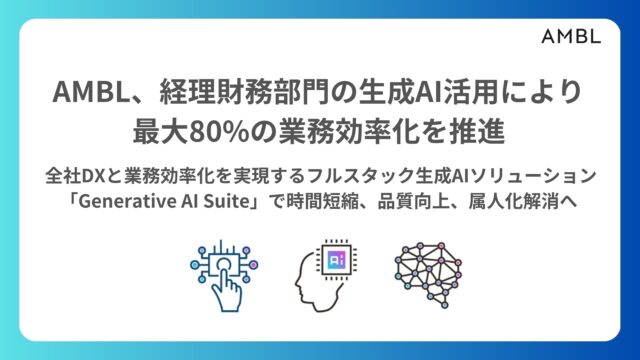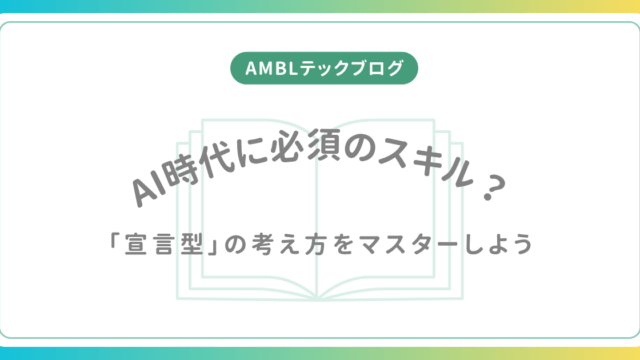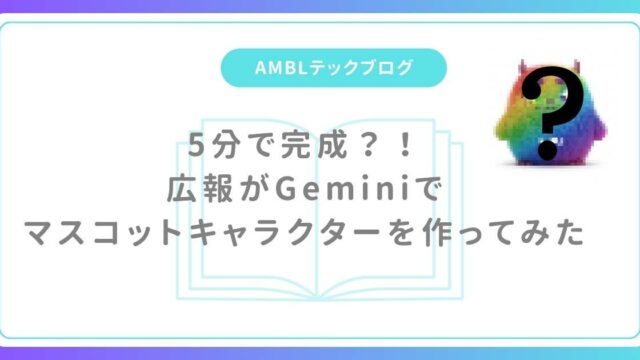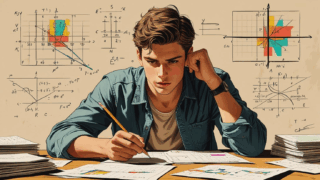こんにちは、AMBL(アンブル)の広報の小野です。
AIを主軸にDXを推進するAMBLでは、さまざまな部署のエンジニアが集まって、最新情報やナレッジの共有を行うslackチャンネルを運営しています。日々のTipsの備忘や技術系トピック、qiitaやzennといった外部メディアのアウトプットの共有、業務や技術的に分からないことの質疑応答なども行っています。
本連載では、チャンネルに投稿された技術系トピックを外部向けに編集して、投稿していきます。
今回は、僭越ながら、広報の私の生成AI活用法を共有させていただきます!
目次
- 広報活動に生成AIの導入率は37.2%
- まずは“壁打ち相手”から。広報活用の「はじめの一歩」
- 「一次情報の壁」を超えるための要約・情報収集術
- 広報ライティングを効率化する3つのテクニック
- 読み手の心に響く文章を書けるのは、人間だけ
広報活動に生成AIの導入率は37.2%
日本広報学会の調査では、国内広報部門における生成AIの導入率は37.2%という結果でした(※)。
「もう4割近くも導入が進んでいるのか…!」とこの数字に、焦りを感じる方もいるかもしれません。しかし、まだ6割以上の広報が本格導入には至っていない、というのもまた事実です。多くの広報担当者が、手探りで活用方法を模索している。今はまさに、そんな「過渡期」と言えるでしょう。
また、同調査によると、生成AIの活用業務トップは「コピー案出し」と「記事要約・情報収集」でいずれも60%以上利用しているという回答でした。
私もコピー案出しや情報収集でよく利用しているので、今回はその2つで使用する際のポイントと、広報ライティングで使用する際の自分なりのコツを、具体的なプロンプト例とあわせてご紹介します。
※ 広報における生成AI導入率37.2%、121社の活用実態を分析(by AdverTimes.)
まずは“壁打ち相手”から。広報活用の「はじめの一歩」
コピー案出しでは、「たたき台」や「発想のヒント」をもらう感覚で使うのがポイントです。
例として、COLORSの記事を作成するという想定で、プロンプトを作成してみました。
プロンプト例
あなたは世界一優秀な広報兼ライターです。検索されやすく、生成AIに興味がある方やエンジニアに読まれるような「生成AIの活用」をテーマにしたテックブログのタイトル案を、20個提案してください。
このプロンプトで出力された回答が下記になります。
出力されたプロンプト
1.【脱・定型業務】エンジニアのための生成AI活用ガイド
2.プロンプトは“呪文”じゃない。開発現場を変える生成AI実践術
3.あなたのコードはもっと速くなる。生成AI時代の開発ワークフロー
4.【Tech Lead必見】チームの生産性を最大化する生成AI戦略
5.LLMを“壁打ち相手”に。次世代のペアプログラミング入門
6.もうコピペで消耗しない。技術文書・設計書作成の自動化
7.エラーログ解析からCI/CD改善まで、生成AIが開発を加速する
8.データサイエンティストが語る、生成AIとデータ活用の最前線
9.アーキテクチャ設計が変わる。生成AIが描く未来のシステム像
10.GitHub Copilotだけじゃない。開発者ツールとしての生成AI活用術
11.【AI時代のスキルアップ】今、エンジニアが学ぶべきこと
12.生成AIで「動くプロトタイプ」を秒速でつくる方法
13.新人エンジニアでもベテラン並み?生成AIがもたらす開発スキル格差の変容
14.コードレビューの負担を減らす。AIとの協業で実現する高品質な開発
15.「なぜ動かない?」を10秒で解決。デバッグを加速する生成AI
16.【実践】生成AIを使いこなすためのプロンプトエンジニアリング基礎
17.AIの限界と可能性。エンジニアが知るべき生成AIの真実
18.スクラム開発に生成AIを組み込む。スプリントの質を高める秘訣
19.インフラエンジニアの救世主?Terraformコードを自動生成するAI
20.【完全版】企画からリリースまで、生成AIと駆け抜ける開発ライフサイクル
私がプロンプトを作成する際に意識しているのは、「生成AIがどんなペルソナなのか」「どんな人に届けたいのか」を明確に指示することです。
もちろん、上記ではまだまだタイトルとしては弱いですが、どの方向性で記事を作成していくかのヒントとしては十分です。
ここから、実際に社内のエンジニアに相談して、読者が本当に読みたい記事はなにかなどさらに深掘りして記事案を考えていく、という流れで進めています。
「一次情報の壁」を超えるための要約・情報収集術
業界動向のリサーチや競合分析は重要ですが、時間がかかりがちです。私の場合、GeminiのDeep Researchを活用して、情報をキャッチアップしています。
プロンプト例
あなたは世界一優秀なリサーチャー兼広報です。最新の生成AIの情報をキャッチアップして、経営および広報部門がキャッチアップする重要度順に列記してください。
これにより、情報収集の時間を大幅に短縮でき、「情報をどう解釈し、戦略に活かすか」という、より本質的な思考に時間を割けるようになりました。
一点、気を付けていただきたいのは、生成AIが出力した情報の「真偽」を必ず確認することです。特に広報活動では、信頼性が命です。AIはあくまでも情報の「整理役」であり、最終的なファクトチェックは私たち人間が行う必要があることを忘れないようにしましょう。
広報ライティングを効率化する3つのテクニック
最後に、私が実際に活用している、具体的なライティングのテクニックを3つご紹介します。これらを組み合わせることで、質の高い文章をよりスピーディに作成できます。
1. ひな型を使用して記事を作成する
広報担当者は社内向け&社外向けのリリースを作成する機会が多々あると思います。
以下のプロンプトは、必要な情報を網羅的に整理し、AIに適切なトーンで文章を生成させることを目的に作成しました。
プロンプト例
プロンプト例:あなたは、~社の広報担当者です。添付のリリース情報を、「リリースひな型or会社トンマナ」にもとづき、プレスリリースとして作成してください。文章は、読者がサービス導入のメリットを具体的にイメージできるよう、事例や利用シーンを盛り込んでください。
また、最後に、会社としてのビジョンや今後の展望を簡潔に加えてください。リリース作成する際は、以下を意識してください。
1.タイトルとリード文で一番の売りがまとめられているか
2.事実を正確に書く
3.結論を先に書く
4.専門用語は極力少なくする
5.広告的な表現や余分な形容詞は削る
6.具体的な数字や根拠を明示する
以下、リリースひな型表記を貼り付け
以前のひな型や会社のトンマナを使うことでより効率化できますし、リリースで意識すべきポイントを明確に指示することで、高品質なアウトプットが期待できます。
2. #や検索ワードを考えてもらう
私自身、ブログやSNSの運用時に付ける#や検索ワードはほぼ生成AIに作成してもらっています。
プロンプト例
あなたは世界一優秀なITインフルエンサーです。添付のこの記事(投稿)がなるべく多くの人やエンジニアに届くよう、関連する#を20個考えて、貼り付けしやすいよう、羅列して表記してください。
こちらは文章と違って、ほぼ間違いない出力が期待できるのでおススメです!
3. 短時間で複数のパターンを生成し、表現の幅を広げる
広報活動では、同じ内容でもターゲットや媒体によって表現を使い分ける必要があります。例えば、ウェブサイト用、SNS用、プレスリリース用、マスコミへのメール文用など、それぞれに適したトーンや文字数が求められます。
プロンプト例
あなたは世界一優秀な広報兼ライター兼インフルエンサーです。添付のリリースを、SNS投稿用の短文にリライトしてください。
一つの記事から複数のアウトプットを効率的に作成することで、広報活動全体のスピードとクオリティを同時に引き上げることができますし、2の#などと組み合わせても効果的です。
読み手の心に響く文章を書けるのは、人間だけ
生成AIは、私たちのクリエイティビティや思考をサポートする強力なツールです。
情報の整理、アイデアの壁打ち、効率的な文章作成といった「得意なこと」をAIに任せることで、私たちは「読者の心に響くストーリーを語る」「信頼関係を築く」といった、広報としてもっとも大切な業務に集中できます。
ただし、コピー案出しの項目で述べた通り、生成AIの出力はあくまで文章のたたき台作成くらいの感覚でいた方が無難です。
正誤含めて最終的な文章チェックは、個人の国語力や文章力によるところが大きく、アウトプットが容易な分、今後の広報としてのスキルはより読解力や文章を組み立てる力が必要になると個人的には思っています。
どんなに優れたAIを使っても、最終的に読み手の心に響くか、メディアに取り上げられるような構成になっているかは、私たち広報の腕にかかっています!
今回は私の活用法をご紹介しましたが、次回は、エンジニアの皆さんのよりテクニカルな活用法などご紹介する予定です。ぜひご期待ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
AMBLは「デジタルの力でチャレンジする人が報われる社会を作る」というミッションのもと、3つのバリューを大切にしています。
称賛と承認: 互いの挑戦を尊重し、認め合うこと。
まず一歩踏み出す: 変化を恐れず、自ら行動を起こすこと。
自分自身に打ち克つ: 他責にせず、困難な状況でも自分と向き合うこと。
これらのバリューが、お客様のDXを推進する私たちの原動力です。
もしこの記事を読んでAMBLの事業や働き方に興味をお持ちいただけたら、ぜひリクルートサイトもご覧ください。
あなたとお会いできることを、心から楽しみにしています。